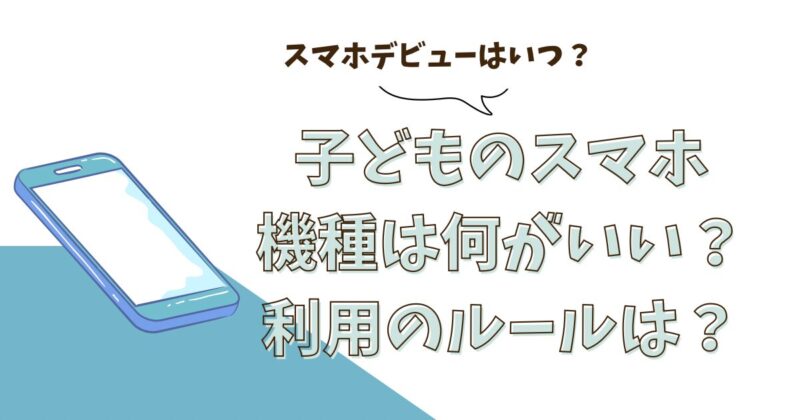子どもにスマホ持たせてる?
──この話題、ママ同士の会話で一度は出てきますよね。
我が家では比較的早い段階でスマートフォン(iPhone)を持たせました。
その度に「もう!?」と驚かれますが、きちんと理由があります。
今回は、スマートフォンを与えるタイミングやキッズケータイとの違い、そして家庭でのルール作りについて、実体験を元にまとめました。
スマートフォンはいつ与えた?
長女がスマホを持ったのは6歳(年長)の頃。
正確には、保育園を卒園する3〜4ヶ月前でした。
当時、長女が入院することになり、ちょうどコロナ禍で付き添い入院ができなかったため、連絡手段が必要になったのです。
病院には事前に確認し、携帯利用の許可をもらったうえで決断しました。
これが、我が家がスマホを導入したきっかけです。

今後は、長女に倣い下の子たちにも小学校入学前にスマートフォンを持たせる予定です。
キッズケータイではなくiPhoneにした理由
キッズケータイは価格が安く、機能が限定されていて安心。
最初は私も「これで十分かも」と思っていました。
それでも最終的にiPhoneを選んだ理由は、以下の通りです。
夫も私もiPhoneユーザーなので、操作を教えやすい点も決め手でした。

iPhone同士だと「メッセージ」や「位置情報共有」が純正アプリだけで完結するので、余計なアプリを入れずに済むのも安心です。
また、長女はiPadも使用しているので操作性も一貫性があり使いこなすのも早かったです。
家庭でのスマホルール

とはいえ、早期にスマホを導入する場合、ルール作りは必要じゃないの?
我が家はスマホに関して厳しいルールは設けていませんが、状況に応じて都度調整しています。

インターネットに流した(流れた)画像や動画などの情報は、自分で回収できないことなどネットリテラシーについても都度話しをしています。
親からの声掛けと意識付け
スマートフォンを持たせることには、メリットだけでなくリスクもあります。
SNSトラブルや依存など、親が見守る姿勢が大切です。
我が家では、「スマホ=自分の所有物ではない」と伝えています。
「このスマホはお父さん名義のものだよ。
お父さんがお金を払って貸してくれているだけ。
大切に使おうね。」
スマホを雑に扱う姿を見た時は、その度に声をかけています。
親の価値観を、日常の中で少しずつ伝えていく意識です。

親の物=親が把握していることを認識してもらいます

でも私が使っているスマホは可愛くしたい!

それは好きにして笑
子どもとスマホは親子の会話がカギ
スマートフォンを与える時期や機種の選び方に正解はありません。
大切なのは、子供の性格・家庭の状況、親の管理の仕方を合わせて考えること。
我が家の場合は「入院中の連絡手段」から始まりましたが、結果的にITリテラシーを早く育てるキッカケにもなりました。
これからスマートフォンを検討している方は、「親子で話し合いながらルールを作る」ことを意識してみてください。

この記事が参考になれば嬉しいです!
ブログの更新確認はホーム画面に追加、もしくはブックマークでお願いします!